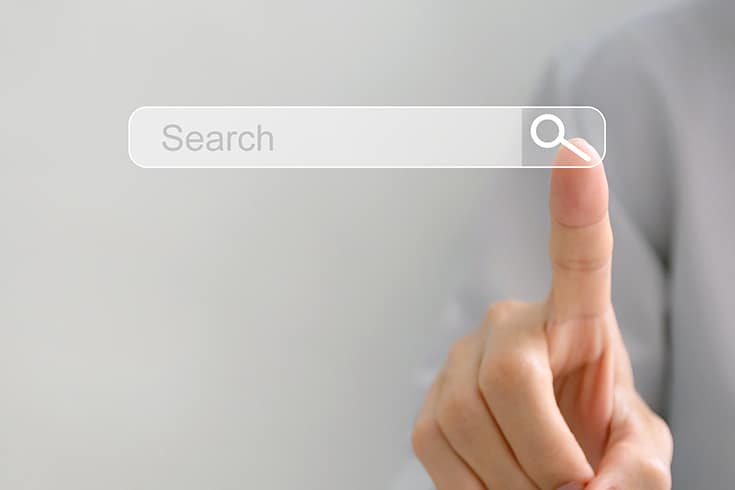死者に対する名誉毀損は成立するのか

名誉を毀損する記事を掲載されたり、誹謗中傷されて社会的評価が低下させられた時、人は損害賠償を請求することができます。では、死者の場合にはどうなるのでしょうか。死者に対する名誉毀損は成立するのでしょうか。名誉毀損に基づく損害賠償請求は、被害者が固有に持つ人格権に基づくことから、遺族が行使できるかが問題になります。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条2項
つまり、「虚偽の事実を適示することによって」「死者の名誉を毀損した者は」罰せられます。
この記事の目次
民法における死者に対する名誉毀損
一方、民法では少々異なります。
民法では、身体、自由、名誉を侵害したときは不法行為が成立し、損害賠償が可能です。ですが、名誉侵害による損害賠償の場合、根拠となるのは、人が社会生活上有する人格的利益を目的とする権利を人格権です。一般的に、この人格権は一身専属権、つまりある人に帰属し、他の人が取得したり行使したりできない権利であり、権利者の死亡によって消滅すると考えられています。
民法での死者に対する名誉毀損に対する考え方を整理し、要約すると、以下のようになります。
- 死者の名誉権を認める見解もあるが、理論的根拠に疑問があり、あえて死者の名誉権を認める実益がない。
- 死者の社会的評価を低下させる事実適示がなされていても、それが遺族の社会的評価を低下させるものと解釈できる場合には、遺族の名誉が毀損されたとみなすことができる。
- 死者の名誉を毀損する記事等が遺族の名誉を毀損すると解釈できない場合には、「個人に対する敬愛追慕の情」を被侵害利益と認める場合がある
したがって、裁判例も2のような遺族固有の人格権、又は3のような敬虔感情の侵害を根拠とするものが多く見られます。
遺族の死者に対する敬愛追慕の情が最初に問題となった事例
最初に死者に対する名誉毀損が問題となった事例は、作家城山三郎の小説『落日燃ゆ』をめぐる訴訟でした。

『落日燃ゆ』は東京裁判で絞⾸刑を宣告された7⼈のA級戦犯のうち、ただ⼀⼈の⽂官であった元総理で外相広⽥弘毅の⽣涯を描いた小説ですが、この中に、広田のライバルと⽬されていた外交官A(故⼈)の私事に関する記述がありました。問題とされた箇所は「相⼿は花柳界の⼥だけではない。部下の妻との関係もうんぬんされた。(潔癖な広⽥は、こうしたAの私⾏に、『⾵上にも置けぬ』と眉をひそめていた)」というものでした。
Aには子供がいませんでしたが、実子同然に可愛がられていたAの甥であるX(原告・控訴⼈)は、この⽂章は、事実無根であり、外務省の部下の妻と姦通をした破廉恥漢として描かれており、これによってAの名誉が害され、Aを実⽗のように敬愛してやまないXは、多⼤な精神的苦痛を受けたとして、城⼭三郎と出版社に対し、謝罪広告の掲載と慰謝料100万円の⽀払を求めて、訴訟を提起しました。
東京地⽅裁判所は、死者に対する名誉毀損表現について、
- 死者の名誉を毀損する⾏為により、遺族等⽣存者⾃⾝の名誉が毀損される場合
- 死者の名誉が毀損されるにとどまる場合
と区別し、
「1の場合は遺族に対する名誉毀損が成⽴するが、2の場合は虚偽虚妄をもって名誉毀損がなされた場合にかぎり違法⾏為となると解すべきである」と判断の枠組みを提⽰し、結論として、本件は2の場合になり、虚偽虚妄であると認定するに⾜りる証拠がない
1977年7⽉19⽇判決
として請求を棄却しました。
Xは、この判決を不服として控訴し、控訴審である東京⾼等裁判所は、
本訴は、死者に対する名誉毀損⾏為により控訴⼈⾃らが著しい精神的苦痛を蒙つたとして、控訴⼈に対する不法⾏為を主張するものと解されるのであるから、前記のような請求権者の問題はない。そして故⼈に対する遺族の敬愛追慕の情も⼀種の⼈格的法益としてこれを保護すべきものであるから、これを違法に侵害する⾏為は不法⾏為を構成するものといえよう。もっとも、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、その後時の経過とともに軽減して⾏くものであることも⼀般に認めうるところであり、他⾯死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移⾏して⾏くものということができるので、年⽉を経るに従い、歴史的事実探求の⾃由あるいは表現の⾃由への配慮が優位に⽴つに⾄ると考えるべきである。本件のような場合、⾏為の違法性の判断にあたり考慮されるべき事項は必ずしも単純でなく、被侵害法益と侵害⾏為の両⾯からその態様を較量してこれを決せざるを得ないが、その判断にあたっては、当然に時の経過に伴う前判⽰の事情を斜酌すべきである。
としつつ、
Aは1929年11⽉29⽇に死亡しているところ、本件⽂章はその死後44年余を経た1974年1⽉に発表されたものであ る。かような年⽉の経過のある場合、右⾏為の違法性を肯定するためには、前説⽰に照らし、少なくとも摘⽰された事実が虚偽であることを要するものと解すべく、かつその事実が重⼤で、その時間的経過にかかわらず、控訴⼈の故⼈に対する敬愛迫慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法⾏為の成⽴を肯定すべきものとするのが相当である。しかして、前認定によれば、本件⽂章に記載された問題の個所が虚偽の事実と認めることはできないから被控訴⼈の⾏為について違法性はなく、控訴⼈主張の不法⾏為の成⽴を認めることはできない。
東京高等裁判所1979年年3⽉14⽇判決
として、控訴を棄却しました。 44年余の時を経た事例だったので、認容はされませんでしたが、「故⼈に対する遺族の敬愛追慕の情も⼀種の⼈格的法益としてこれを保護すべきもの」であることを認めた最初の裁判例です 。
遺族の名誉を毀損したとする事例

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示した場合罰せられます。
一方で、殺人事件に関する新聞の誤った報道が被害者ばかりでなく、被害者の遺族(母)の名誉をも毀損したとして、損害賠償請求が認容された事例があります。
被害者は1972年に結婚し、夫と事件現場となったアパートに入居し、スーパーでパート勤務し、男女関係で特に噂にのぼることもなく真面目に平穏な生活を送っていました。精神病院に入院していた犯人(男性)が1976年寛解退院し、同アパートに入居したところから、顔見知りとなりましたが、隣人として犯人と日常の挨拶をかわす程度で、特に接触もなくすごしてきました。ところが、犯人は妄想を抱き、被害者との間に恋愛関係や肉体関係があると思い込み、被害者が三角関係に悩み、自分の結婚申し込みを受け入れてくれないのだと思い込み、被害者を刺殺し、夫に重傷を負わせました。
静岡地方裁判所は、静岡新聞がこの事件を「三角関係のもつれ」という見出しで報じ、記事の本文中で「内縁の妻」や「犯人がスーパーの店員をしている被害者と最近親しくなり」と表現し、被害者があたかも犯人との間に複雑な恋愛関係を有するばかりか、肉体関係を有していたかのような印象を一般読者に与えたことについて、これらが全て虚偽であり被害者の社会的評価を低下させるものであって、名誉を毀損するものであると認めました。
さらに、原告である被害者の母の名誉も毀損されたか否かにつき判断し、本件記事掲載以後、本件記事を真実と受け取った被告新聞の一般読者が多数居住し、原告も在住する地域社会において、被害者の母として、世俗的関心の的となったことにより世間をはばかり、肩身の狭い毎日を送っていた事実が認められるとして、
社会生活上ある者の名誉の低下が一定の近親者等の名誉にも影響を及ぼすことのある実情を考慮すると、新聞記事によって死者の名誉が毀損された場合には、一般に、社会的評価の低下はひとり死者のみにとどまらず、配偶者や親子等死者と近親関係を有する者に及ぶことがあることは肯認しうるところであるといわねばならない。
静岡地方裁判所1981年7月17日判決
とし、「新聞記事の掲載が虚偽の事実をもって死者の名誉を毀損し、これによって近親者の名誉をも毀損するに至る場合には、右記事掲載は近親者に対する不法行為を構成するものというべきである」として、被害者の母は、被害者の名誉回復が得られない以上、被告に対し名誉毀損による不法行為責任を求めることができるとして、慰謝料30万円の支払いを新聞社に命じました。
遺族の死者に対する敬愛追慕の情を侵害したとする事例

死者の名誉毀損は死者自身に対する不法行為とはならないが、遺族の死者に対する敬愛追慕の情の侵害(遺族の人格権侵害)として不法行為が成立するとされた事例があります。雑誌「フォーカス」が1987年1月、「エイズ死『神戸の女性』の足どり」という見出しで、葬式の最中に無断で盗み撮りした遺影写真とともに、死亡した女性(亡○○)をわが国最初の女性エイズ患者として紹介し、同女性が主に外国人船員相手の売春バーに勤め、同所では、週に一人か二人のペースで客を取り、なじみ客を他のホステスと共有することもあった等の内容を報道する記事を掲載しました。
これに対し、死亡した女性の両親が、亡○○及び自分たちの権利ないし法益を侵害されたとして訴訟を提起したのですが、大阪地方裁判所は、「原告らは、本件では被告らの行為により、死者である亡○○自身の名誉権、プライバシーの権利及び肖像権等の人格権が侵害された旨主張する。しかしながら、このような人格権は、その性質上、一身専属権であると解すべきところ、人は死亡により私法上の権利義務の享有主体となる適格(権利能力)を喪失するから、右人格権もその享有主体である人の死亡により消滅するものである。そして、人格権については、実定法上、遺族又は相続人に対し、死者が生前享有していた人格権と同一内容の権利の創設を認める一般的な規定も死者につき人格権の享有及び行使を認めた規定もない」として、「死者の人格権はこれを認めることができないから、亡○○自身の人格権が侵害されたとする原告らの主張は採用できない」としました。なお、死者の肖像権が認められなかった点も、注目されます。
そこで、次に原告らの人格権、亡〇〇に対する敬愛追慕の情が侵害されたかどうかについて判断したのですが、記事内容のほとんどが事実とは認められず、記事の内容が社会的評価をはなはだしく低下させるものであり、亡○○の名誉は、本件報道によって著しく毀損されたとしました。
本件報道は、亡○○の名誉を著しく毀損し、かつ生存者の場合であればプライバシーの権利の侵害となるべき亡〇〇の私生活上他人に知られたくないきわめて重大な事実ないしそれらしく受け取られる事柄を暴露したものであるが、このような報道により亡○○の両親である原告らは、亡〇〇に対する敬愛追慕の情を著しく侵害されたものと認められる。したがって、本件報道は、原告らの右人格権を侵害するものである。
大阪地方裁判所1989年12月27日判決
このように判断し、大阪地方裁判所は雑誌「フォーカス」に対し、慰謝料100万円、弁護士費用10万円、合計110万円の支払いを命じました。
慰藉料請求権は相続の対象となるか
順序が逆になったかもしれませんが、AがBに対し名誉を毀損する発言をし、その後Bが死亡したという事例があり、この慰藉料請求権は相続の対象となるかという問題については、最高裁判所の判例があります。原判決は、慰謝料請求権は一身専属権であり、被害者の請求の意思の表明があつたときはじめて相続の対象となるとしたのですが、これは公平の観念および条理に反し、慰藉料請求権の相続に関する法理を誤ったものである、と最高裁判所は判示しました。
最高裁判所は、
ある者が他人の故意過失によって財産以外の損害を被った場合には、その者は、財産上の損害を被った場合と同様、損害の発生と同時にその賠償を請求する権利すなわち慰藉料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、これを行使することができ、その損害の賠償を請求する意思を表明するなど格別の行為をすることを必要とするものではない。そして、当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰藉料請求権を相続するものと解するのが相当である。
最高裁判所1967年11月1日判決
とし、「慰藉料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものであるけれども、これを侵害したことによって生ずる慰藉料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はない」として、慰藉料請求権の相続を認めなかった原判決を破棄し、原審に差し戻しました。
まとめ
名誉が毀損されたり、プライバシーを侵害されたりしたとき、死者の名誉だからといって、それらを遺族等が甘受しなければならないということはありません。死者は訴訟を提起することはできませんが、遺族又はそれと同視し得る人であれば、遺族の名誉が毀損された、または敬愛追慕の情が侵害されたと主張することが可能です。
とは言え、こうした場合の損害賠償請求は裁判で行われることがほとんどです。裁判上の手続きは複雑かつ専門的な知識が要求されます。もし亡くなった人物に対する名誉毀損による損害賠償請求を考えているのであれば、一度専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
カテゴリー: 風評被害対策