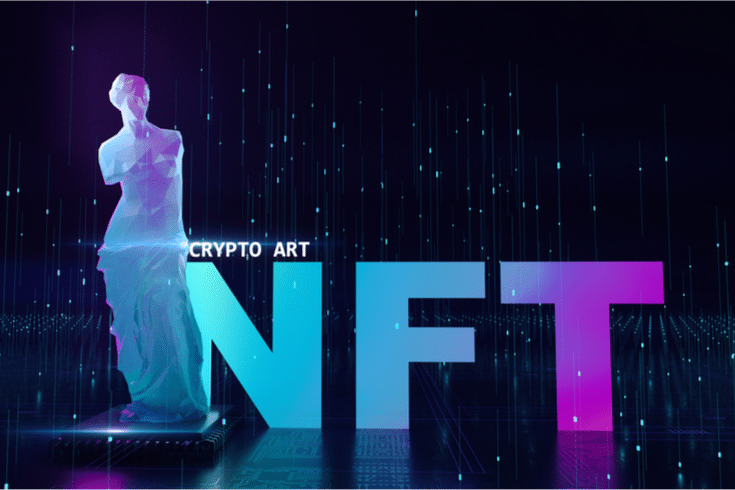論文の盗作の基準は?判例を解説

当たり前のことですが、書籍を出版したり、ネット上で公表する際に、他者の文章をコピー&ペーストしただけのものやあるいはそうした部分を多く含むものを、自分の文章として提出することは許されません。適切な「引用」の要件を満たしていない場合には、「盗作」とされ、重大な不正行為とみなされます。
では、論文の場合は、どのように盗作であるか否かが判断されているのでしょうか。
ここでは、「論文」の盗作が裁判で争われ、盗作であると認められた事例を解説します。
この記事の目次
盗作が認められた事案
a大学b学術院の准教授の地位にあった原告が、大学に対し、大学が原告に対して論文の盗用等を理由として行った懲戒解任は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであると主張しました。そこで、自己が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、不払い賃金の支払いを求めた事案があります。
事案の背景
原告は2000年4月1日、被告であるa大学を経営する学校法人と雇用契約を締結してa大学c学部専任講師に就任し、2002年4月1日、同大学c学部助教授に就任し、その後本件学術院准教授となりました。専門分野は経営学、専攻は経営戦略です。 原告は2001年、a大学c学部が発行する学術誌である「u誌」において、「○○」と題する英文の論文(以下A論文)を発表するとともに、2002年4月1日のa大学c学部助教授への昇任に際し、A論文を助教授への昇任論文として提出しました。また、A論文は、2001年度ないし2002年度の日本学術振興会の科学研究費補助金(「科研費」)の助成対象である研究課題の研究実績として報告され、科研費の助成事業データベースにも同報告が掲載されました。
さらに、原告は2003年、「u誌」において、「△△」と題する英文の論文(以下B論文)を発表しました。

懲戒解任に至る経緯
a大学b学術院のD教授は、2014年4月中旬、原告に対し、A論文の内容が他の論文と類似しているという外部からの指摘があったことを伝えました。さらに、同年5月中旬頃、a大学学術院長兼c学部長であるE教授とc学部教務主任であるF教授に対し、A論文が,アメリカの研究者であるGが1998年に執筆した博士学位請求論文である「□□(以下「本件対照論文A1」)と酷似しており盗作が疑われること、また同じGが2000年に雑誌に投稿した論文である「◎◎」(以下「本件対照論文A2」)にも酷似しており、原告がこれを盗用したのではないかと数年前から大学院生の間で噂になっていたようであると伝えました。
これを受けて、F教授は学術資料検索エンジンでA論文と本件対照論文A1及び本件対照論文A2の類似性について調査していたのですが、偶然、原告が執筆したB論文が、H他1名(以下「Hら」)が1999年に雑誌に投稿した英語論文である「●●」(以下「本件対照論文B」)に類似しているのではないかとの疑惑を抱きました。
これにより設置された調査委員会は、2014年9月3日、本件各論文は、原告がアメリカの大学院在学中に研究会で入手した未公刊の原稿、具体的にはA論文についてはGが1997年に研究会で発表した未公刊の原稿(以下「本件原著論文A」)を、B論文についてはHらが1997年頃に研究会で発表した原稿(以下「本件原著論文B」)を基に作成されたものであると推定され、原著者らが本件各原著論文を基に執筆し公表した論文(本件各対照論文)と原告による本件各論文がほぼ同一の文章であり、原告は2度にわたって同様の行為をしており、人の目に触れにくい未公刊論文が利用されていることから、本件論文不正疑惑に係る原告の行為は、故意に論文を盗用したものであると判断されるとの報告をしました。
同年9月9日、本件学術院の臨時教授会において設置された査問委員会は、本件学術院長であるE教授に対し、10月13日、原告の行為は原著論文の盗用に当たると判断しました。なお、原告がそのような原著論文の盗用行為を2回繰り返していること、盗用により不正に作成した論文を科研費の研究成果として報告、公表していること、当該論文を助教授に昇任する際の昇任論文として利用していること、これらの研究不正を撤回し解消する措置がいまだ講じられていないことを重視して、懲戒解任とするのが相当であると判断するという報告を行いました。その後、11月21日、理事会の決議により懲戒解任とすることを決定し、同日、その旨を原告に通知しました。
原告の主張
原告は、この懲戒解任が不当であり、無効であると主張して、自己が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、不払い賃金の支払いを求めて、裁判を提起しました。
原告は、以下の理由から本件原著論文Aを故意に盗用したものでないと主張しました。A論文は、原告がH大学大学院在学中に参加した研究会で配布された未発表原稿(本件原著論文A)を参考に、取引費用経済学の分野における先行研究の成果を紹介する目的で執筆したいわゆる「展望論文(review article)」であること、A論文において本件原著論文Aを引用していることからも明らかなように、原告には、本件原著論文Aを故意に盗用する意図はなかったこと、原告自身がその前に執筆した論文を引用するなど、A論文の執筆において原告自身の貢献も一定程度あったという点などです。
なお、レヴュー(展望)とは、研究の過程として、研究テーマに関する先行研究を概説し、紹介して、自分の研究の位置づけを明確にするために行うものです。ほとんどの学術論文には、導入部分に、短いレヴューのセクションがあります。レヴューのみを一つの論文、展望論文として発表することも可能です。ただし、先行研究の紹介であり、引用であることを明らかにしなければなりませんし、先行研究の紹介ですから、引用文献リストがとりわけ重要となります。しかし、A論文には、引用文献リストのようなものはありませんでした。
B論文については、原告がh大学大学院在学中に、学内の研究会で配布されたレジュメである本件原著論文Bを参考に、本件原著論文Bで示されたサンプルについて独自にデータを収集、分析した上で執筆したものであり、原告自身がその後B論文を基に研究を発展、展開していることからも明らかなように、原告には、本件原著論文Bを故意に盗用する意図はなかった、と主張しました。ただし、B論文の執筆に当たり原告が独自に収集、分析したデータは、パソコンのハードディスクの破損により消失しており、原告は、これを本件調査委員会に提出することはできませんでした。
また、原告は、本件懲戒解任は、原告が本件各論文を発表してからそれぞれ11年後及び13年後になされたものであるが、告発期限に関する規定は存在しないにせよ、研究活動における不正が指摘された場合に反証可能性を確保するという観点からしても、当該行為から長期間が経過した後に調査や懲戒処分を行うことは許されないというべきであり、実際、B論文の執筆に当たり原告が収集、分析したデータは、パソコンのハードディスクの破損により消失していた、とも主張しました。

裁判所の判断
裁判では、論文の類似性についての検討は、1行の全部が一致している又は実質的に一致と認められるときは1行一致しているものと扱い、1行の単語数において過半数が一致しているときは0.5行一致しているものと扱い、これら以外の場合には一致がないものとして扱うという方法で行われました。
その結果、A論文については、裁判所は、本文の行数の70.2%が本件対照論文A1とほぼ一致しており、挿入されている図表3点もほぼ一致していることをあげ、A論文は、対照論文A1を再製したというべきものであることを認め、本件原著論文Aの紹介を目的とした論文であることを示す記載や、A論文が本件原著論文Aを紹介する論文(原告の主張するところの「展望論文」)であることを表明する記載はなく、むしろA論文における考察が著者である原告自身の研究成果であることを示唆する記載がなされていること等をあげ、A論文は、原告が本件原著論文Aを故意に盗用して執筆したものである、と認めました。
B論文については、裁判所は、同様に分析してみた結果、本文の行数の87.9%が本件対照論文Bとほぼ一致しており、挿入されている図表5点も完全に一致していることをあげ、B論文は、本件対照論文Bを再製したというべきものであることを認め、本件原著論文Bの引用すら行われていないことをあげ、B論文は、原告が本件原著論文Bを故意に盗用して執筆したものである、と認めました。
これらに基づき、裁判所は、
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし(学校教育法83条1項)、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する責務を負っていること(同条2項)に照らせば、大学に所属する研究者は、より高度な倫理性の保持が要請されるというべきである。
原告が行った本件論文盗用行為は、他者の研究成果を踏みにじるとともに、自らの研究業績をねつ造するものであって、上記研究者としての基本的姿勢にもとる行為に当たり、研究者としての資質に疑問を抱かせるものであるし、わずか3年の間に同様の行為が2回も繰り返されていること、いずれの行為も不正が発覚しにくい研究会で配布された未公刊のレジュメに基づき行われていることからしても、その悪質性は顕著というべきである。
東京地方裁判所2018年1月16日判決
として、原告の請求をすべて却下しました。
裁判所は、「当該行為から長期間が経過した後に調査や懲戒処分を行うことは許されない」とする原告の主張に対しては、研究不正から長期間が経過している場合に、当該研究者の防御を図る観点から、懲戒処分を行うことに慎重を期すべき場合があること自体は否定できないとしつつも、研究不正の中には、研究成果とされたデータのねつ造や改ざん、盗用等様々な態様のものが含まれ、その悪質性の程度や不正の指摘に対する具体的な防御の方法も個々に異なるのだから、行為から長期間経過後に懲戒処分を行うことが一律に否定されるものではないとしました。
そして、本件論文盗用行為については、各論文が各原著論文を盗用したものであることはその表記及び体裁のみをもっても一見して明らかなのであるから、本件論文盗用行為から長期間を経過していることをもって原告の防御に実質的な不利益が生じたとはいえない、としています。

まとめ
論文の場合には、本裁判におけるような「1行ごとの分析」によって、盗作であるか否かを判断する方法が可能ですが、句読点や括弧等を除いた文字が全体としてどれだけ同一であるかによって判断することもあります。
盗作は悪質な不正行為ですし、発覚すると重大な責任を問われかねませんから、他者の文章を利用する際には、適切な引用の要件を満たすように、注意する必要があります。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、著作権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: 知的財産権