プログラムのソースコードの著作権は誰に帰属するのか
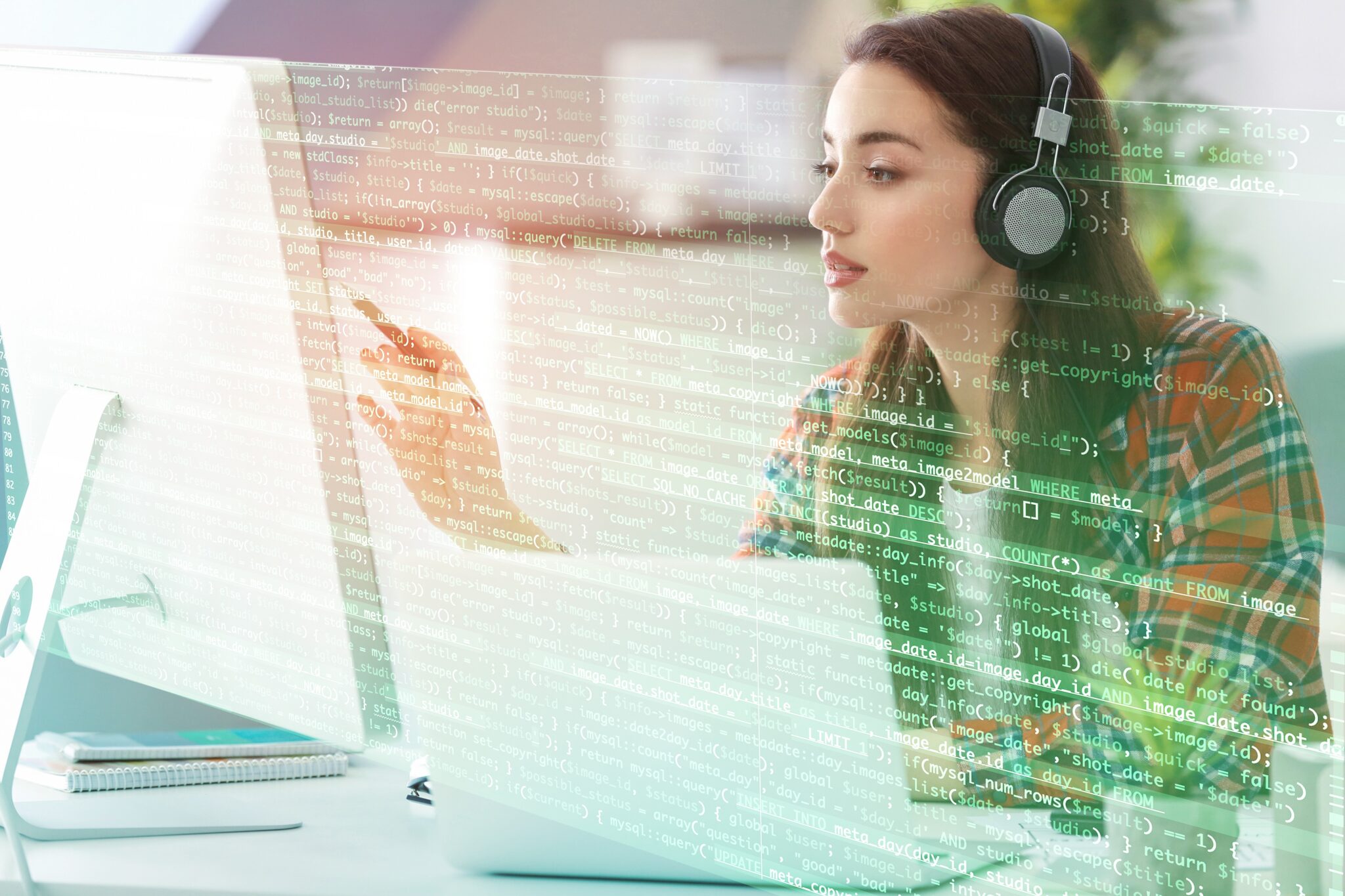
著作権法において、プログラムは「著作物」に該当することが明示されています。
しかし、小説や絵画などの著作物と異なり、システム開発関連のプログラムは、通常、複数の従業員や多数の法人が協力して作成しています。
そのため、権利関係が曖昧になりがちで、複雑な紛争に発展しやすいのが実態です。
そこで本記事では、プログラムの著作権が誰に帰属するのかという点について、争いになりやすいポイントと解決策を、判例とともに解説します。
この記事の目次
著作権法とは

著作権法は、小説や映画、絵画等の著作物に対する著作者の権利を保護し、創作へのインセンティブを付与することで、「文化の発展」に寄与することを目的とした法律です。
また、著作権法の特徴として、特許法などとは異なり、国に登録等をすることなく、著作物を創作した時点で当然に権利が発生するという点が挙げられます。
「プログラムの著作物」と「ソースコード」の関係
著作権法では、小説や絵画と同様に、「プログラム」は「著作物」に該当し、著作権法の保護対象になりうることが法律に明記されています(著作権法第10条1項9号)。
第十条(著作物の例示)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
著作権法第10条1項9号
・・・
九 プログラムの著作物
また、「プログラム」については、以下のように定義されています。
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの
著作権法第1条1項10号の2
他方で、「ソースコード」とは、法律上定義されてはいないものの、一般的に、コンピュータに対する指令を人間が記述する言語(JavaScriptやPythonなど)で表現したものをいいます。
コンピュータは、このソースコードを変換(コンパイル)して機械語にすることで、指令を実行しています。
したがって、「プログラム」の上記定義に照らせば、ソースコードは、著作権法上の「プログラムの著作物」として保護されている、といえるわけです。
システム開発の場面で起こり得る
著作権法上の問題

システム開発の場面において著作権が問題となるケースは、次の2類型に大別されます。
誰が著作権者になるのか
著作権が帰属する人は誰かというのは、著作権譲渡の成否やタイミングなどに関する問題です。
システム開発の場面では、ベンダー側も多数の作業者が分担しながらプロジェクトを進めていく場合が多いため、権利の帰属主体は曖昧になりがちで、複雑な紛争に発展するケースが見受けられます。
また、ベンダーからユーザーに成果物が引き渡される場面でも、著作権が譲渡が認められるかなどをめぐって、争いが起きることがあります。
著作権を侵害したかどうか
著作物の複製や翻案などに伴う「著作権侵害の成否」の問題です。
他人の作った”よく似た”プログラムが、「参考にしただけ」なのか「コピー」なのかといった問題がこれにあたります。
なお、プログラムに関する著作権侵害の問題については、下記記事で詳細に解説しています。
そこで本記事では、上記のような問題の全体像を踏まえた上で、「誰が著作権者になるのか」について焦点を絞り、以下解説していきます。
ソースコードの著作権の帰属に関する基礎知識

著作権について、帰属や開発の移転、契約書等に関連した基礎知識を解説します。
著作権は「創作した人」への帰属が原則
まず、著作権が誰に帰属するかについて整理します。
プログラムの場合にも、小説や絵画などの著作物と同じように、著作者(著作物を創作した人)に権利が帰属するのが原則です。
しかし、著作権法上、職務著作に該当する場合には、使用者である法人等に権利が帰属すると定められています。
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
著作権法第15条2項
つまり、ベンダーの従業員として業務中に作成したプログラムの著作権は、ベンダーに帰属するということです。
開発の委託は著作権の移転を意味しない
著作者人格権を除く著作権は、移転や譲渡が想定される権利です。
しかし、この点において注意を要するのは、報酬を払って開発業務を委託することと、著作権の譲渡は別問題であるということです。
有償で開発を委託していることから、納入とともにプログラムの著作権そのものも譲渡されると誤解されるケースがあります。
しかし、あくまで著作権法上は、「創作した人に権利が帰属する」というのが原則であり、「創作にかかる費用を負担した人に権利が帰属する」というものではありません。
したがって、委託者が権利まで取得しておきたいのであれば、事前に契約書を作成して、その旨も契約の内容として取り決めておくことが必要です。
契約書等における著作権譲渡に関する条項の有無
著作権譲渡に関する取り決めについては、以下のように場合分けできます。
- 契約書等で著作権の譲渡について定めがある場合
- そもそも契約書がない場合や、契約書等において著作権譲渡の条項が設けられていない場合
契約書等で著作権の譲渡について定められていれば、当然、相手方から著作権の譲渡が受けられます。著作権は、譲渡可能な権利であり、著作権譲渡につき著作権者が自らこれを承諾しているためです。
しかし他方で、そもそも契約書がない場合や、契約書等において著作権譲渡の条項が設けられていない場合など、著作権譲渡に関する明示的な取り決めがない場合、著作権が譲渡されることはありえないのでしょうか。
以下では、著作権譲渡に関して明示的な取り決めがない場合の著作権譲渡の成否について判断した裁判例をもとに、解説します。
著作権の譲渡に関して明示的な取り決めがない場合の裁判例

著作権譲渡に関して明示的な取り決めがない場合については、著作権譲渡を肯定した裁判例と否定した裁判例があります。その違いはどこにあるのでしょうか。
著作権の譲渡を肯定した裁判例
システム開発と異なる分野ではあるものの、次の裁判例が参考になります。
駅の入口に設置するモニュメントのデザインをめぐり、モニュメントのデザインを創作した原告と、当該デザインを一部改変してモニュメントを建設した県及び県から業務委託を受けたデザイン設計会社との間で、著作権侵害の有無が争われました。
この事案では、原告と被告らとの間に著作権譲渡に関する明示的な取り決めがありませんでした。被告らは、原告が事実上、当該デザインの著作権が被告帰属すること及び当該図面の改変を承諾していたことから、著作権侵害は認められないと主張しました。
このように、本事案では、著作権譲渡の成否が争点になりましたが、この点について、裁判所は、以下のように判示しました。
これらの事実(デザイン料の支払いを受けていた事実や、設計協議の手続きを経ないでデザインを更に変更することをも了承していた事実など)と,本件モニュメントは,岐阜駅南口に設置することが当初から予定されており,それ以外の用途が考えられないものであったことをも考慮すれば,控訴人は,本件モニュメント製作に当たり,被控訴人会社との間で,その提供した図面等に描いたモニュメントのデザイン(本件著作物に当たるもの)について,これが美術の著作物に当たり,著作権により保護されるとしても,被控訴人会社に対し,その著作権を譲渡すること(被控訴人会社は,その後,上記委託業務契約に基づき,被控訴人県に対し,すべての著作権を譲渡することになる。)を,少なくとも黙示的には合意した上で,上記モニュメントに関するデザインを提案し,その対価として,被控訴人会社から,控訴人が要求したとおりの金額でその報酬を得た,と認めるのが相当である(仮に,著作権譲渡の合意について明確な合意があったと認めることが困難であるとしても,控訴人は,少なくとも,被控訴人会社が,被控訴人県の委託に基づいて,控訴人のデザインを一部採用した本件モニュメントのデザイン設計業務を行い,被控訴人県がこれに基づいて本件モニュメントを建設することを当初から基本的な前提条件として黙示に了承した上で,上記のとおり本件モニュメントについてのデザインを提案し,その対価を得たことを認めることができることは,明らかである。)
東京高判平成16年5月13日
すなわち、著作権譲渡に関する明確な合意がなくとも、業務の遂行過程における様々な事情を考慮した上で、著作者が著作権を譲渡することにつき「黙示の合意」をしたと判断されれば、著作権譲渡が認められる、といえます。
著作権の譲渡を否定した裁判例
他方で、同様に著作権譲渡に関する明示的な取り決めがない場合に、著作権譲渡を認めなかった裁判例もあります。
この事案では、被告にソフトウェアの開発を委託した原告が、被告に対し、当該ソフトウェアのソースコードを引き渡すべき契約上の義務を怠った債務不履行があるとして、債務不履行に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案です。
被告は、本件ソースコードの引渡義務を否定する前提として、著作権の譲渡を否定したため、本事案でも著作権譲渡の成否が争点となりましたが、裁判所は、以下のように判示して、著作権の譲渡を認めませんでした。
(1) 本件委託契約の履行に伴う著作権移転の合意の不存在
大阪地判平成26年6月12日
原告の主張は,本件委託契約に基づき,本件ソフトウェア及び本件ソースコードの著作権の譲渡が合意され,これに伴い,ソースコードの引渡義務も発生するというものである。
前記1(2)によると,被告が,本件ソースコードを制作したものであり,本件ソースコードの著作権は原始的に被告に帰属していると認めることができる。
その一方で,前記1(2)(3)の見積書等,原告と被告との間で取り交わされた書面において,本件ソフトウェアや本件ソースコードの著作権の移転について定めたものは何等存在しない。
前記1のとおり,被告は,原告に対し,本件ソースコードの開示や引渡しをしたことはなく,原告から本件ソースコードの引渡しを求められたが,これに応じていない。
また,原告にしても,平成23年11月に至るまで,被告に対し,本件ソースコードの提供を求めたことがなかっただけでなく,前記1(7)のとおり,原告担当者は,被告に,本件ソースコードの提供ができるかどうか問い合わせているのであり,原告担当者も,上記提供が契約上の義務でなかったと認識していたといえる。
以上によると,被告が,原告に対し,本件ソースコードの著作権を譲渡したり,その引渡しをしたりすることを合意したと認めることはできず,むしろ,そのような合意はなかったと認めるのが相当である。
上記判示では、「黙示の合意」といった言葉は出てきませんが、著作権譲渡に関する明示的な取り決めがないことを前提に「著作権を譲渡…することを合意」したとは認められないと判示していることから、やはり「黙示の合意」の有無により判断しているものといえるでしょう。
その上で、この事案において著作権譲渡に関する「黙示の合意」が否定された主な理由は以下のとおりです。
- 著作物であるソースコードの開示や引渡しが、当初求められていなかった
- ソースコードの開示・提供の可否について問い合わせていた
すなわち、この事案では、著作権譲渡の合意あったとするならば、わざわざ著作物の提供の可否を問い合わせるのではなく、著作権者として、当初から著作物の引渡しを求めていたはずである、といったが判断されたのです。
このように、著作権の譲渡に関する明示的な取り決めがない場合には、当事者の意思がどのようなものであったと考えるべきか、当事者の言動等から事案に即して合理的に判断されるため、事前に誰が著作権者であるかを予測しにくいといえます。
したがって、契約書等で事前に著作権者を明確にしておくことが、紛争を回避するためには重要と言えるでしょう。
ソースコードの著作権者を明確にするための手段とは

ソースコードの著作権者を明確にするための手段を3点解説します。
対象となっているプログラムの開発者を特定する
ITシステムは通常、多数のプログラムの集積で成り立つものであり、複数名で分担しながら作り上げていくものです。したがって、まずは争いとなっているプログラムの開発者が誰であるのかを調査し、特定することが必要となります。
この場合には、ベンダー側の作業スケジュールなどに記された担当者の欄に誰の名前が記されていることや、ソースコードに付されたコメント欄の作成者情報などが有力な手がかりとなることが考えられます。
開発者と会社の関係を整理する
前述のとおり、職務著作に該当するのであれば、ソースコードを書いた人ではなく、その人の使用者である法人等に著作権が帰属します。
プログラムの開発が、開発者の所属する会社の指揮監督のもとで行われている場合には、職務著作性が比較的容易に認められるでしょう。
しかし他方で、私的な人間関係に基づく「お手伝い」のような関係を想定すると、職務著作の該当性が争いとなる可能性があります。
著作権譲渡の合意を事前に検討する
委託者がベンダーから権利を譲り受けたと主張するような場合には、その立証責任を負うことになります。また、著作権譲渡の成否は、当事者間で自由に取り決めが可能な事項でもあります。
したがって、こうした争いを事前に回避するためには、システム開発を委託する段階であらかじめ、著作権の帰属や譲渡、ベンダーからの利用許諾の範囲などについても取り決め、契約書に明示しておくことが望ましいと言えるでしょう。
なお、経産省モデル契約と呼ばれる、官庁が公開するシステム開発の契約の雛形には、下記のような規定が参考として記載されています。
第45条(納入物の著作権)
納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、甲又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、乙に帰属するものとする。(以下略)
経済産業省「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守運用)〈第二版〉」
※甲はユーザー、乙はベンダー。上記雛形は一例であり、ベンダーに著作権を帰属させるものですが、ユーザーに著作権を帰属させるという契約も可能です。
まとめ :ソースコードに関する著作権の帰属は契約書等で明確にしよう

システム開発における著作権の帰属をめぐる争いは、事前に契約書を作成することで、未然に防ぐことが可能です。
しかし、契約書の作成は法的知識が必要とされます。もし、契約書の作成でトラブルを事前に回避したければ、法律のノウハウを持っている弁護士に頼むのが安全でしょう。
著作権者の帰属トラブルでお困りの際は、当事務所にお問い合わせください。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、著作権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。


































